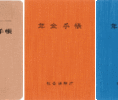国民健康保険とは地域で加入する健康保険制度で、一般的に自営業等を行っている方が多く加入されている健康保険です。
国民健康保険は、在職時の健康保険のような健康保険と異なり、被保険者や被扶養者という区別は無い為、専業主婦・専業主夫、学生や未成年者等の加入者全員が被保険者本人となります。(退職者医療制度に係る場合をのぞく)
なお、加入は世帯ごとで、手続きについては世帯主がまとめて行いますが、健康保険証は各人に1枚づつ交付されます。
また、会社都合などによる退職の場合は国民健康保険料の軽減制度があり、軽減の届出を行うと離職日の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30%として算定された保険料が適用されます。
加入の条件
他の健康保険に加入していないこと
加入できる期間
75歳になるまで
保険料について
国民健康保険の保険料は、前年の所得ならびに市区町村によって異なります。
その為、自分が国民健康保険に加入した際の保険料については、市区町村の窓口にて相談して確認して下さい。
加入の手続き期限
退職の翌日から14日以内に届出を行って下さい。
手続きの窓口
市区町村の役場窓口にて手続きが行えます。
手続きに必要な書類等
国民年金に加入するには退職した会社より以下の書類作成してもらい、市区町村に持参してください。
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
なお、上記の書類がない場合は手続きを進める事が出来ませんが、退職直後に治療費が発生し全額自己負担した場合でも、国民健康保険に加入した後に払い戻しの手続きを行えば、3割の自己負担額を差し引いた7割が返還されます。
その他、状況により以下の物を一緒に持参して下さい。
- 国民健康保険被保険者証(既に同じ世帯で国民健康保険加入者がいる場合)
- 印鑑(国民健康保険の世帯主以外が届出する場合)
- 年金証書(国民年金以外の公的年金を受給している場合 ※65歳未満の人のみ)
- 各医療証(乳幼児・障がい者・ひとり親家庭等。家族の人が持っている場合も)
健康保険に関する関連記事

家族の被扶養者になる
家族が加入している健康保険の被扶養者(扶養家族)になる場合は、新たな保険料の負担が無い為、扶養家族になれる場合は健康保険を選ぶ際の最良の選択肢と言えます。 加入の条件 加入申請時からを基準として、今後の...
国民健康保険の保険料を軽減
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)の方は、国民健康保険料を軽減する制度があるので、国民健康保険に加入した際は軽減の申請を行いましょう。 対象者について ...
在職時の健康保険を任意継続
「健康保険の任意継続」とは在職中に加入していた健康保険に引き続き加入できる制度です。 在職時の健康保険を継続する為、任意継続することで退職後も在職中と同じ給付を受けることが出来、扶養家族についても継続して保険...手続きに関する関連記事

失業保険をもらう最初の手続き
失業保険をもらう為には、退職した会社から離職票を受け取った後に、最初の手続きとなる「雇用保険の受給手続き(求職申込み)」を行う必要があります。 初めての手続きの際はどのように手続きを行えば良いか分からず、二の...
離職票をもらう際の注意点
離職票は退職した会社から郵送もしくは手渡しで退職者本人に渡される書類で、失業保険(雇用保険)の受給手続をする際に必要となる書類です。 失業保険は退職日からもらえる訳ではなく、雇用保険の受給手続きが遅くなった日...
就業促進定着手当
再就職すると前職より待遇が悪かったり、同等の雇用条件であっても試用期間があるなどの理由により、前職の給与より低くなったなんて話はよくあります。 しかし、早期再就職して再就職手当をもらった人は、下がった給与差額...知識に関する関連記事

再就職手当が100万円!
再就職手当とは早期再就職の促進を目的に作られている制度で、失業保険(雇用保険の基本手当)を貰っている人が、早期に安定した職業に就いた場合や事業を開始した場合に一括で支給される手当の事を再就職手当といいます。 ...
失業保険受給までの手続きの流れ
退職理由が会社都合と自己都合では、基本的な手続きの流れは変わりません。 しかし大きく異なる点は、自己都合の場合は3ヶ月の給付制限がある為、給付開始時期が大きく異なります。 また、実際の失業保険の給付は、...